胆汁培養は有用か

急性胆管炎において、ERCP時に胆汁培養は採取されていますか。当院ではほぼ採取しています。
今回の論文は、軽症〜中等症の急性胆管炎において胆汁培養の有用性を検証した多施設RCTです。
【方法】
2015年8月から2023年9月まで、韓国の12の三次病院で実施。血液培養のみの実験群と胆汁培養と血液培養の対象群に1対1に割り当てたRCT。
対照群は血液と胆汁の培養結果に基づいて抗生物質を投与されたが、実験群は血液培養の結果のみに基づいて治療された。
主な結果は、ショック、急性腎障害、精神状態の変化、および急性呼吸困難の存在によって評価された臓器不全率。
二次的な結果は、全死因死亡率、再介入の頻度、抗生物質の使用期間、および入院期間。
非劣性マージンは10%。
【結果】
対照群(n = 215)と実験群(n = 213)。
臓器不全は、対照群で28(13.0%)、実験群で27(12.7%)に発生(差:-0.350%[95%信頼区間、-6.690から5.990]、p>0.999)。
死亡率は、対照群(7人)で3.3%、実験群(5人患者)で2.3%(-0.908% [-4.033から2.216]、p = 0.782)。
再介入率は、対照群で31(14.9%)、実験群で26(12.2%)(-2.677% [-9.155から3.801]、p = 0.504)。
抗生物質治療期間は、対照群(12.8 ± 8.0日)と実験群(11.3 ± 6.5日)(-1.500日[-2.840から-0.160]、p = 0.037)。
入院期間は、対照群(14.1 ± 11.0日)と実験群(12.2 ± 9.0日)(-1.900日[-0.380から0.000]、p = 0.046)。
結果を見ると、臓器不全/全原因による死亡/再介入の必要性は変わらないようですね。
治療期間と入院期間は実験群で短くなったようです。
RCTなので内的妥当性(今回の結果が、試験として集めた集団に対して真実と言えるか)は高いのは当然です。気になるのは一般化の可能性(試験のために集めた集団の特性は、その地域の実臨床の集団の特性と一致するか)です。試験集団と我々の実臨床集団が大きく異なれば、RCTといえども実臨床に適応することはできません。
今回の試験では、12の病院で428例を集めるのに8年も掛かっています。各施設が均等に症例を登録したと仮定すると、各施設は1年で5例ほどしか登録していないことになります。当院では年間350例ほどが胆管炎と診断されますが、その中から5例しか登録していないとしたらどうでしょうか。その5例が350例の特性を代表していると自信を持てるでしょうか。RCTでは、割り付けた2群では患者特性が均等になりますが、試験のために集めた集団が実臨床集団を代表しているかということ(さきほどの"一般化の可能性")が常に問題となります。本試験は、一般化の可能性は低いと考えたくなります。
(少し蛇足ですが、本試験は韓国だけで行われました。これを欧米やアフリカなどの白人/黒人にも適応できるかということも問題となります。韓国や日本は高齢社会なので、若年人口が増え続けている新興国などにも適応できないかもしれません。このように “試験集団を抽出する元となった母集団が、それ以外の母集団の特性とマッチするか"という考えを、外的妥当性といいます。あるRCTの結果を、自施設やでの実臨床に当てはめていいかは、内的妥当性→一般化可能性→外的妥当性と考えていくことになります。)
本RCTの試験結果を私の施設に当てはめていいかですが、「RCTなので当然内的妥当性は高いが、一般化の可能性は低そう。韓国と日本は黄色人種で年齢構成も近いため外的妥当性はあると思われるが、一般化の可能性が低いため試験結果を鵜呑みにはできない。」という印象でした。

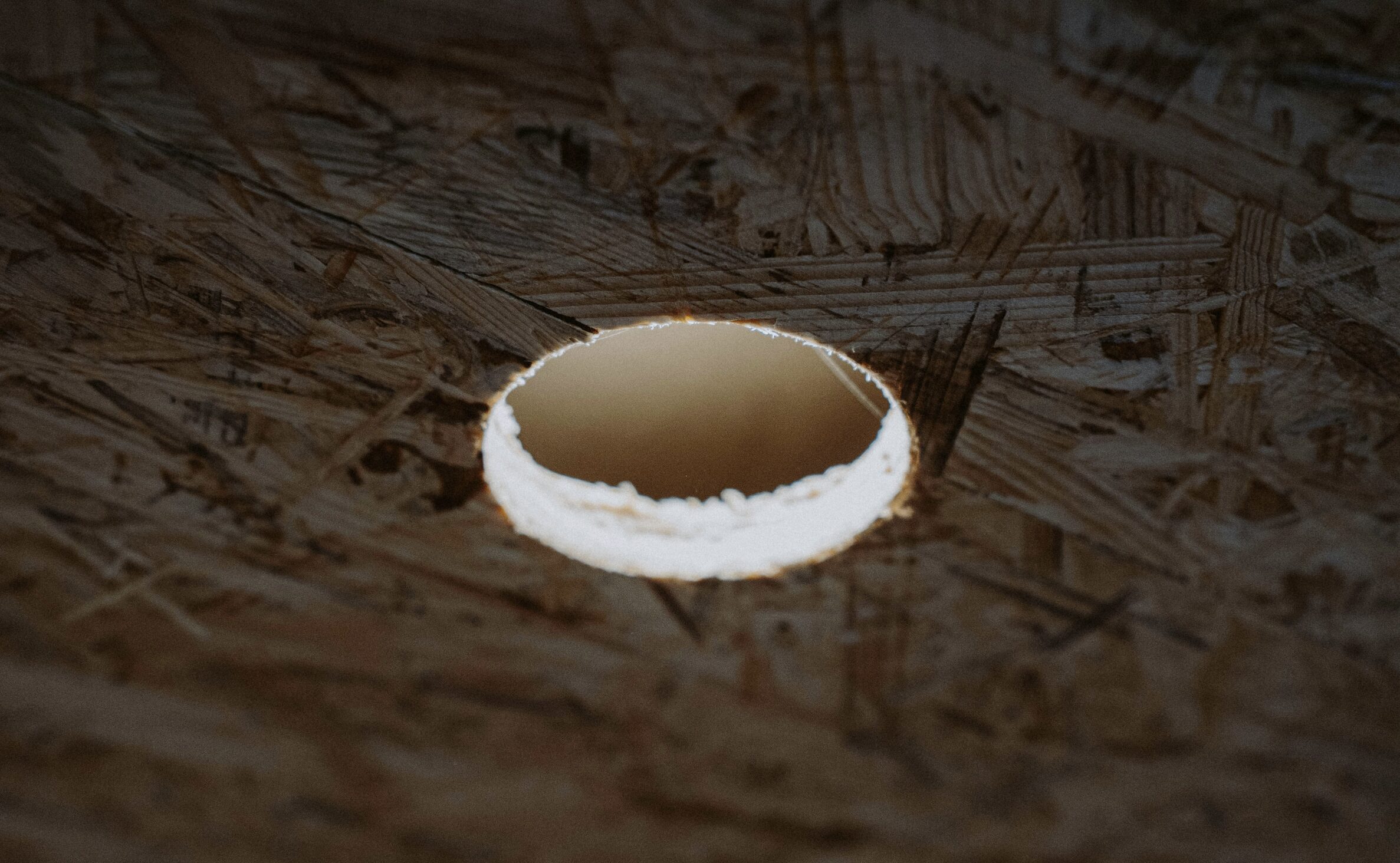






ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません